2時間コース(歴史)その1
START: 富海駅
徒歩30分
大内輝弘自刃の地(茶臼山)

永禄12年(1569)毛利氏が九州の立花城を攻めている際、大内輝弘は豊後から秋穂へ上陸し、山口を占領した。 しかし毛利の軍勢が引き返して来たため、豊後に逃げ帰ろうしたが船がなく、陸も海も毛利氏の軍勢に囲まれて、逃げるとしたが船がなく、陸も海も毛利氏の軍勢に囲まれて、逃げる場所がなくなり、富海と牟礼末田の境の茶臼山で自刃した。
富海駅から約1.2km(途中急な「たちばな坂」を上る)
徒歩20分
富海海岸

明治40年に富海海水浴場は県下で最初に開かれ、明治・大正・昭和と多くの人々で賑わった。南沙織が歌った「17才」は、富海海水浴場を舞台に誕生した。前に広がる周防灘のかなたに大分県国東半島を望むビュースポットである。 ※写真は橘坂から見た富海海水浴場
茶臼山から約1km(途中急な「たちばな坂」を下る)
徒歩5分
伊藤・井上両公上陸遺蹟碑

元冶元年(1864)、英国留学中の伊藤俊輔・井上聞多は、外国艦隊が下関を攻撃するという新聞記事をロンドンで見て、英国留学を中断して急きょ帰国。6月24日密かに富海西町飛船問屋入本屋(入江礒七宅)に上陸し、身支度を整え、外国艦隊との戦い回避を訴えるべく藩主毛利敬親の居る山口へ向った。
富海海岸から約0.6km
徒歩3分
大和屋政助船蔵

江戸時代、富海から大阪への飛脚船・飛船(とびふね)が頻繁に接岸し、多くの物や人が出入りした大和屋政助の船蔵が今に残る。政助は勤王の志厚く、文久3年(1863)に天誅組の変で敗れた公家中山忠光(明治天皇の叔父)を船蔵に匿い、元冶元年(1864)には長州の内戦で追われた高杉晋作を嵐の中、飛船を出させて下関へ送った。
伊藤・井上両公上陸遺蹟碑から約0.3km
徒歩2分
富海本陣

江戸時代山陽道沿いの富海本陣は、宮市から福川本陣への途中の半宿であり、大名行列の休憩、あるいは長崎奉行やオランダ人(出島居留)、日田御用金運送などの比較的小規模な人数の宿泊に利用された。
大和屋政助船蔵から約0.2km 船蔵通りから旧山陽道に出る
徒歩5分
国津姫神社

承平5年(935)、國津姫大明神のご宣託により、その社殿を脇地区船岡山より現在の社地に移転し、造営。祭神は宗像大社、厳島神社と同じ海の女神三柱で、田心姫命(たごりひめのみこと)、湍津姫命(たぎつひめのみこと)、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)。
富海本陣から約0.6km
徒歩15分
GOAL: 富海駅
2時間コース(歴史)その2
START: 富海駅
徒歩5分
伊藤・井上両公上陸遺蹟碑

元冶元年(1864)、英国留学中の伊藤俊輔・井上聞多は、外国艦隊が下関を攻撃するという新聞記事をロンドンで見て、英国留学を中断して急きょ帰国。6月24日密かに富海西町飛船問屋入本屋(入江礒七宅)に上陸し、身支度を整え、外国艦隊との戦い回避を訴えるべく藩主毛利敬親の居る山口へ向った。
富海駅から約0.6km
徒歩3分
大和屋政助船蔵

江戸時代、富海から大阪への飛脚船・飛船(とびふね)が頻繁に接岸し、多くの物や人が出入りした大和屋政助の船蔵が今に残る。政助は勤王の志厚く、文久3年(1863)に天誅組の変で敗れた公家中山忠光(明治天皇の叔父)を船蔵に匿い、元冶元年(1864)には長州の内戦で追われた高杉晋作を嵐の中、飛船を出させて下関へ送った。
伊藤・井上両公上陸遺蹟碑から約0.3km
徒歩2分
富海本陣

江戸時代山陽道沿いの富海本陣は、宮市から福川本陣への途中の半宿であり、大名行列の休憩、あるいは長崎奉行やオランダ人(出島居留)、日田御用金運送などの比較的小規模な人数の宿泊に利用された。
大和屋政助船蔵から約0.2km 船蔵通りから旧山陽道に出る
徒歩2分
登録有形文化財清水家主屋

明治の中頃に建築されたた古い建物であり、歴史的景観と造形に優れ、その保存、活用が特に必要なものとして、平成27年に国の登録有形文化財に登録された。現在、毎週水曜日の午前中、「とのいちマルシェ」が清水家住宅において開催され、農産物をはじめ食品・雑貨類など色々なものが販売されている。
富海本陣から約0.2km
徒歩3分
国津姫神社

承平5年(935)、國津姫大明神のご宣託により、その社殿を脇地区船岡山より現在の社地に移転し、造営。祭神は宗像大社、厳島神社と同じ海の女神三柱で、田心姫命(たごりひめのみこと)、湍津姫命(たぎつひめのみこと)、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)。
清水家住宅から約0.3km
徒歩11分
伝説毛利時親卿墓

毛利時親は毛利元就より11代前の毛利当主で、安芸吉田毛利の始祖。暦応4年(1336)、時親は家督を孫に譲り出家して名を了禅(りょうぜん)と改め、吉田を出て西へ向い富海村に入り、この地で老後を過ごし、死したであろうといわれている。江戸時代後期に、墓が付近の畑で発掘され、墓石には表に大江時親、裏に了禅、と刻まれている。
国津姫神社から約1km
徒歩12分
光福寺

光福寺は、平重盛の會孫の金剛坊南岳(こんごうぼうなんがく)大僧都が、壇の浦の戦いにおいて源氏に敗れた平家一門の菩提を弔うために、建暦元年(1211)に開基したとされており、当時は、石原地区の御堂山(みどうやま)、春日野(かすがの)、三石(みついし)一帯に及ぶ壮大な寺院であったと伝えられている。堂内の薬師如来像は昔から「石原の御薬師様」と信仰されている。
伝説毛利時親卿墓から約1km
徒歩30分
GOAL: 富海駅
5時間コース(自然散策)
START: 富海駅
徒歩12分
ビュースポット橘坂(たちばななざか)

新地地区のJR踏切を渡ると、旧山陽道「橘坂」に差しかかる。昔より、坂の途中で立ち止れば、浜辺、八崎岬、はるか先の九州と180度パノラマの素晴らしい眺めが広がる。この坂を上りきった所に「手掛け岩」と呼ばれる岩があり、これに触ると健康になると親しまれており、ここからの眺めも良い。
富海駅から約1.2km
徒歩12分
ビュースポット富海海水浴場

南沙織が歌った「17才」は、富海海水浴場を舞台に誕生した。快晴の空気が澄んだ日には、前に広がる周防灘のかなたに、大分県国東半島が望まれ、素晴らしい景色が現れる。
橘坂から約1.2km
徒歩6分
船蔵通り

江戸時代、山陽道に近接した富海浦から大阪へ、物や人を迅速に運んだ飛船(とびふね)が接岸した海岸線と大和屋政助船蔵が今に残る。
富海海水浴場から約0.6km
徒歩2分
旧山陽道

江戸時代富海村を通る山陽道は、東の椿峠から西の牟礼村おこん川まで東西1里3町(約4200m)の行程であった。この道のほとんどが、今も、道幅、曲がりに変わりなく残っており、富海本陣跡を中心に宿場町の面影が見える。
船蔵通りから約0.2km 大和屋政助船蔵そばの石段を上がり、旧山陽道に出る。
徒歩20分
ビュースポット戸田山

周南から椿峠を越えて国道2号を下ると瀬戸内海に南面した富海の美しい景色が目に飛び込んでくる。
富海本陣跡から約1.8km 旧山陽道を椿峠に向かい、富海観光農園前から国道2号歩道(上り)に上がった所
徒歩15分
ビュースポット光福寺薬師堂

ここから見える瀬戸内海が美しい快晴の空気が澄んだ日には、遥かかなた大分県国東半島の山々が望め、目を見張る。田んぼの上に広がる海がとてきれいである。
ビュースポット戸田山から約1.2km
徒歩20分
昼食(AIMA)

「美味しい野菜のランチと季節の果実パフエ」カフエは富海の野菜と果実をふんだんに使い、富海だかできる料理とスイーツが賞味できる。
ビュースポット光福寺から約0.6km
徒歩25分
琴音の滝

琴音の滝は水源を大平山に発し、流れ落ちた水は鮎子川を経て瀬戸内海へ広がる。明治42年、春の新緑、夏の清涼、秋の紅葉に注目し、滝への道を整備したのが当時の村長小野田陸馬である。料亭もでき、文人墨客をはじめ多くの人が訪れた。初夏、近くの茂みに銀竜草が咲く。
AIMAから約2km AIMAから富海公民館へ向かい、同館前の道を右折、門前坂道を琴音の滝入口まで上る
徒歩20分
ビュースポット梶野

富海北西部の梶野地区、その山手のみかん畑の上から眺める景色は目を見張る。三方を山に囲まれ瀬戸内海に南面する富海の町並みが美しく、町並みを縫って江戸時代の山陽道が今に残り、国道2号、JR山陽線という主要交通が走る。東に連なる山の合い間から上る朝日が美しい。
琴音の滝から約1.5Km
徒歩20分
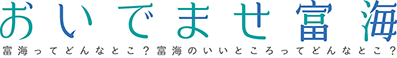
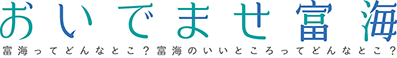
最近のコメント